 リハビリテーション科
リハビリテーション科
診療科の紹介
スタッフの構成 (2025年4月時点)
医師2名(うち専門医1名)、理学療法士24名、作業療法士11.5名、言語聴覚士3名
高度急性期に特化した当院の役割を果たすため、入院に特化した急性期リハビリテーションを行っています。外来リハビリテーションは院内からの紹介のみに限らせていただいております。
急性期リハビリテーション
- 脳卒中センターでは、発症24時間以降早期の離床を図り、早期からのリハビリテーションを行い、早期の転・ 退院を支援しています。
- 整形外科疾患に対しては、術翌日からのリハビリテーション開始を基本とし、早期退院を目指しています。
- 救命救急センターでは早期離床リハビリテーション加算を取得し、全ての患者に入院時からのリハビリテーションを行っています。集中治療室における離床プロトコールを作成し、人工呼吸器管理の短縮、在院日数短縮を目指しています。また、早期に治療が終了した患者の自宅退院可否の評価、他科転科後のリハビリテーションの継続により在院日数短縮を目指しています。
- 脳神経外科では、脳外傷患者、脳腫瘍をはじめとする開頭術の術前評価、術後の離床と評価を行っています。
- 脳神経内科では、パーキンソン病などの神経筋疾患の入院患者に対して転倒予防、日常生活機能維持のための運動指導、生活指導を行っています。
- 心臓血管外科、循環器内科と共にプロトコールを作成し、心臓血管外科術後、心筋梗塞、心不全、急性大動脈解離の心臓リハビリテーションを実施しています。運動負荷試験を実施することで運動耐容能の評価を実施しています。
- 循環器内科と協働し心不全患者のリハビリテーションを行っています。心不全の離床のためのプロトコールを看護師と共有し、治療後の早期退院を目指しています。
- 上記以外の診療科の患者に対しては、臥床時間の長い患者について主治医からのコンサルテーションによりリハビリテーションを実施し、治療後の早期の自宅退院を目指しています。転院の必要性の判断、家族見学の実施などにより方針決定を支援しています。
- 新生児内科に入院している低出生体重児のリハビリテーションを行っています。呼吸状態安定のためのポジショニング、発達を促すための四肢の運動や刺激の入力などを行い、周産期医療への寄与を目指しています。
がん患者に対するリハビリテーション
- 血液内科と協働し、入院して化学療法を行う血液がんの患者にリハビリテーションを行っています。退院時にADL(日常生活動作)の低下を起こさず、継続した化学療法を受けていただくことを目的としています。
- 乳腺外科との協働で、乳がんの手術を受ける全ての患者にリハビリテーションを実施しています。手術後の肩関節可動域制限(手が上がらない)の改善と、リンパ浮腫の予防が目的です。退院後も自宅で続けていただき、外来で肩関節可動域の改善を確認して終了しています。
- 食道がんの術後は、他のがんの術後に比較して合併症、特に呼吸器合併症が多いとされています。外科との協働により食道がんの手術を受ける全ての患者に術前から呼吸リハビリテーションを開始し、術後もリハビリテーションを行い、呼吸器合併症の予防と早期の自宅退院に取り組んでいます。
地域連携の推進
- 回復期・生活期のリハビリテーションについては近隣の病院や施設で継続できる連携システムを構築しています。
- 北多摩南部保健医療圏域のリハビリテーション関係職種向け研修会を実施しています。
- 東京慈恵医科大学附属第三病院リハビリテーション科が行っている東京都北多摩南部保健医療圏高次脳機能障害者支援事業に協力しています。
- 武蔵野運動器リハビリテーション研究会を通じて、当院整形外科医師と北多摩南部保健医療圏の診療所で働く医師、当科職員と地域リハビリテーション関連職種と連携することで整形外科疾患の連携を進めています。これにより圏域内診療所との連携の強化、当院の在院日数の減少、通院患者さんの地域への引継ぎを図っています。
- 武蔵野市内で市内在勤のリハビリテーション関連職種百数十名で武蔵野市PT・OT・ST協議会を設立、運営しています。市内のリハビリテーションに対するニーズに応じて地域ケア会議や、武蔵野市ケアリンピックなどに参加、リハ関連職種の教育を行っています。これらの活動を通じて市内のリハビリテーション関連職種の連携を密にしています。
今後の課題/目標
当科の課題は、高度急性期病院のリハビリテーション科としての急性期リハビリテーションの推進と、地域がん診療連携拠点病院としてがんリハビリテーションの推進です。脳神経疾患と整形外科のリハビリテーションは、回復期リハビリテーション病院や整形外科クリニックなど他の医療機関でも実施可能ですが、他医療機関で行えない疾患として、がんと心疾患、特に心不全への取り組みを進めることが課題です。さらに最近では、高齢化に伴う廃用予防への対応も課題となっています。これらの社会情勢、医療情勢に応じて、求められる業務をバランスよく行っていくことを目標とします。一方でワークライフバランスも大事です。当科のスタッフは、有給休暇を定期的に取得し、男女を問わず産休・育休を取得しています。介護や育児と仕事の両立、産休・育休・介護休暇を希望通りに取得でき、長く働ける職場を目指します。
地域リハビリテーション支援センター
東京都の『地域リハビリテーション支援事業』の北多摩南部医療圏の指定医療機関として認定を受けています。事業の一環として、介護保険関連機関からのリハビリテーションに関する相談を受け付けています。
スタッフ紹介
常勤医師数
2名
スタッフの構成
医師2名 (うち専門医1名) 、理学療法士24名、作業療法士11.5名、言語聴覚士3名 (2025年4月時点)
部長:秋元 秀昭 (あきもと ひであき)
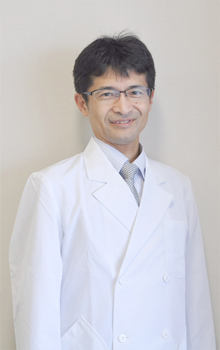
専門領域
- リハビリテーション治療一般
- 高次脳機能障害のリハビリテーション
資格等
- 日本専門医機構認定リハビリテーション科専門医
- 日本リハビリテーション医学会認定臨床医
- 日本専門医機構認定脳神経外科専門医
- 東京都身体障害者福祉法第15条指定医
- 義肢装具等適合判定医研修会修了
- がんリハビリテーション研修会修了
- 回復期リハビリテーション病棟協会修了
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了
- 両立支援コーディネーター基礎研修
- 急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理にかかる医師研修会修了
医師:京谷 美月 (きょうや みつき)
専門領域
- 脳神経内科
資格
- 日本専門医機構認定内科専門医
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了
診療実績
昨年度までの実績
療法別件数
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 理学療法件数 | 61,426 | 56,905 | 62,210 | 61,115 | 51,913 | 49,885 |
| 作業療法件数 | 31,582 | 26,311 | 26,719 | 26,452 | 24,105 | 23,126 |
| 言語療法件数 | 3,113 | 2,725 | 6,546 | 6,433 | 5,819 | 5,946 |
| 早期離床リハ件数 | 1,696 | 3,301 |
種類別延べ患者数
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 脳血管リハ | 19,632 | 15,342 | 14,066 | 15,220 | 13,951 | 18,172 |
| 運動器リハ | 14,924 | 9,723 | 11,174 | 10,449 | 11,514 | 11,390 |
| 心大血管リハ | 2,055 | 2,544 | 2,637 | 3,703 | 4,192 | 5,115 |
| 呼吸器リハ | 1,400 | 2,026 | 5,076 | 5,711 | 5,041 | 4,352 |
| がんリハ | 632 | 947 | 926 | 605 | 728 | 651 |
| 廃用症候群リハ | 47 | 570 | 919 | 1,057 | 1,333 | 1,627 |
| 合計 | 38,690 | 31,152 | 34,798 | 36,745 | 36,759 | 41,307 |

